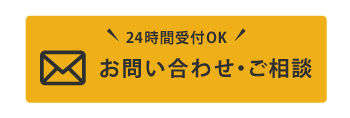初めての外国人採用の流れ(日本にいる外国人雇用)
2018-12-11
2023-11-12
初めて日本にいる外国人を採用する雇用主様や採用担当者様から、採用から内定、ビザ申請の手続きについてよくわからないというご相談をよくいただきます。
ここではビザ申請前後の流れを就労ビザ専門の行政書士がかんたんに説明しています。
![]()
はじめての外国人採用の流れ(日本にいる外国人雇用)
外国人を雇用する場合、日本人とは異なる外国人特有の手続きが必要なシーンが発生します。
最も異なる点は、外国人を雇用するためには適切な就労系のビザを取得するということです。
面接に進む前に、まずは採用を検討する外国人が就労可能な要件を備えているか、採用しようとしている職種でビザを取得できるかという事前調査から始めましょう。
![]()
日本にいる外国人雇用の流れ
STEP1 事前調査
外国人を現場の仕事では採用できないの?
ここでは詳しい説明は省略しますが、建設現場や飲食店での接客など現場でのお仕事で採用をお考えの場合、「特定技能」というビザをご検討することになります。
このビザは、外国人本人は技能実習からの移行か、日本語試験と特定技能試験の両方に合格し企業等から内定をもらう必要があります。受け入れ企業への要件も非常に多く外国人に対する数々の支援が要求されますので、自社で支援することができない場合、外部機関へ支援を委託する必要があるなど一般的な就労ビザより手続きや支援がとても煩雑です。
なお、応募者が身分系と呼ばれる次の1~4のビザをお持ちの場合は就労制限がありません。どのような職種でもすぐにでもフルタイムで働くことができます。
|
外国人雇用で注意すべき点はこちら
![]()
(在留資格と就労可否に関するチャート)
STEP2:外国人の募集開始
事前調査で就労ビザが下りる可能性がある場合、募集を開始します。外国人採用を常時行っていない企業や採用担当者様は、以下の募集方法を参考にしてください。
■ 求人媒体とその特徴
自社ホームページ | 貴社を何かのきっかけで知った方が貴社名で検索してからサイトに訪れる、というプロセスを経ることが多いので、貴社名を知っている人からのアプローチがほとんどです。求人効果が高くない反面、費用は安く抑えることができます。
自社ホームページの1ページに採用情報を載せても効果はほぼ期待できません。自社で採用専用サイトを構築し、アクセスしてきてくれた人にこちらからアプローチすることや、他の求人ツールと掛け合わせるなど仕組みを重層的にすることで効果を上げることが可能です。
多方面に自社サイトのリンクを張り、自社へアプローチすることのできる経路を多く確保することが必要です。日本にいてもエンジニアなどは日本語が苦手な場合も多いので、多言語化された企業サイトは効果的ツールになり得ます。
他社で働いていた人材を、転職活動で中途採用というながれもあります。SNSと連動させたり、これまであまり活用されてこなかったツールとの併用で外国人雇用というケースが、今後増えていくことが予想されます。 |
| SNS | フェイスブックなど投稿による広告を出したり、カテゴリーを絞って広告を出すこともでき、費用対効果が良いと言われます。
応募者はバラエティに富むので、必ずしも求める人材が応募してくるとはいいがたいですが、リアルタイムな情報更新が可能なので、双方向性があることはメリットです。自社のフェイスブックページなどで求職者に対して有意義な情報発信でフォローしてもらえるコンテンツ作りが大切です。
IT業界などは、他の業界より比較的このSNSから直接応募してくるケースが多く、リンクトインほかSNSからダイレクトに自己アピールして採用に至るケースもあります。 外国人コミュニティによって使用頻度の高いSNSは全く異なるので、採用を希望する国籍の外国人が使用するSNSを事前調査することがおすすめです。
・フィリピン:Facebook |
ハローワーク等公的機関 (外国人雇用サービスセンター等) | 無料で利用できるので費用が抑えられることと、応募してくる外国人の属性を把握しておけることがメリット。最近では無料就職セミナーも開催され、その他ハローワークインターネットサービスに求人を公開するとIndeed社でその求人が無料で公開されるようになったのでぜひ利用してみてください。
雇用する日本人がハローワークは日本人が職を探すというイメージから外国人雇用の際に認知されていない部分がありますが、外国人を雇用に関して充実したサービスがあるので、ぜひ活用したいところです。外国人雇用サービスセンターに関しては、東京・大阪・名古屋・福岡の大都市にのみ設置されています。公的機関の情報なのでやや融通性に欠け、自社ホームページとは異なり、内容変更が容易ではないことはデメリットではあります。
・東京外国人雇用サービスセンター
上記東京外国人雇用センターの新宿外国人雇用支援・指導センターでは、身分系と呼ばれる日本人の配偶者、永住者、永住者の配偶者など就労制限のない外国人と、アルバイトを希望する留学生に特化した支援および情報提供をしています。
|
| 教育機関の求人情報 | 大学や専門学校、日本語学校等教育機関の求人情報は無料で掲載できるところが多く、応募者のバックグラウンドを把握したうえで採用活動ができます。また、学校の求人情報を見る学生は比較的優等生が多いという声もあります。学生課や就職課などにコンタクトをとってみてください。
ただし、クローズドの限られた情報であるため、閲覧される絶対数が多くありません。学校によっては掲載を断られたり、手続きに手間がかかることもあるので、要事前確認が必要です。
下記サイトでは外国人を多く受け入れている大学を掲載していますので、これらの大学の学生課や就職課に求人を出してみることも一つの案です。 |
| 外国語フリーペーパー・新聞 | 日本には数多くの国のフリーペーパーがあり、普段あまり意識しないところですが、他の媒体では難しいケースでも採用したい国籍に絞って求人情報を掲載できます。
不特定多数に情報を拡散するので、こちらからアプローチするというよりも、求める人材が応募してくるのを待つことになります。この媒体の特性上、日本語に不安のある人も応募してくる可能性はあります。その他以下のような大手英語雑誌・新聞などの媒体に求人広告を掲載する方法もあります。
|
| 新卒・転職求人サイト | 日本の新卒採用活動と同じような時期に外国人新卒留学生向けのセミナーやイベントが多数開催され、大量に柔軟で融通の利く求人募集ができる反面、費用は高価。採用前にセミナーなどの説明会・相談会で面接前に話をする機会が設けられていることは双方のメリット。どちらかというと中企業~大企業向けの人材採用方法です。
優秀な人材は外国人特化サイトにエントリーすることも多いですが、獲得競争は熾烈です。また、サイトによっては効果にばらつきもあり、自社が採用したい人材を獲得するにふさわしいものを見極めることが必要です。
もっと小規模なコミュニティサイトを利用する場合、個人間のオークションサイトの中で求人告知ができるところがあるので、小規模で地域限定で採用する場合などに活用できます。 |
| 人材紹介会社 | 柔軟で希望するような人材を選択できます。コストは高価ですが、求める人材にかなり絞って採用活動をすることができるので、希望する人材のイメージをできるだけ明確に伝えることで、不要な書類選考や面接にかけるコストを削減できます。
ただし紹介会社のクオリティーはさまざまで、採用することが難しい外国人を紹介される可能性もゼロではありません。したがって紹介会社の選定がまずはポイントとなります。信頼できる顧問先の士業や過去に紹介会社を通して雇用経験のある経営者等から、信頼できる紹介会社を紹介してもらいましょう。 |
STEP3:書類選考
学歴について
学歴については、海外の短期大学卒以上の学歴で日本の短期大学士相当以上の学位を取得していること又は日本の専門学校卒以上の学歴で専門士以上の学位を取得している必要があります。学歴要件を満たす方は職歴要件は不要です。
学歴については国ごとに教育体系が異なるため、海外で大学を卒業していても日本の学士相当と認められないこともあります。
ご参考までに中国の学校系統図を掲載します。他の国についても外国人応募者の大学卒業ということばをそのまま鵜呑みにせず、学位証書などから確認することをおすすめします。外国人ご本人も学歴を満たしていないという認識がないことが多々あります。
職歴について
学歴要件を満たさない場合、一定の職歴を満たす方はビザ申請をすることができます。学歴要件での申請とは異なり、実務経験でのビザ取得は難易度が高いとお考え下さい。
職歴は予定される活動が「技術・人文知識・国際業務」のうち「技術・人文知識」に該当する場合は10年、「国際業務」に該当する場合は3年の職歴が必要です。この年数には大学や高等学校、中等教育学校の後期課程や専修学校(海外の教育機関も含む)で関連する科目を専攻した期間があれば、その期間も加算することができます。
実務的には現地で就労していた企業から「在職証明書」(退職証明書)を発行してもらい提出することになりますが、過去に証明書の偽造が横行したことからこの証明書のみでは疎明資料として認められないこともあります。また、働いていた企業や店舗が倒産などしている場合、在籍状況を証明できないので申請することができません。
なお、真正の在職証明書が発行された場合であっても、在職していたことを補強する資料提出があるほうが許可の可能性は高まるとお考え下さい。
STEP4:面接
面接では基本情報として次のようなことを確認するようにしましょう。
面接時の基本確認事項
|
学歴と専攻の確認
就労ビザが許可されるためには、大原則として外国人の学歴(専攻)と職務内容に関連性があることが非常に重要となります。学んだ内容と一定の関連性がある職務内容であれば許可されますが、全く関係がなければ許可されません。
外国人の学歴(専攻)と職務内容の関連性があるかないかわからない場合は、「卒業見込証明書」や「成績証明書」を提出してもらえばより詳しく何を学んだかわかります。外国人本人には学校などから原本を取得しておくことをお願いしておきましょう。就労ビザ申請の際、これらの書類はコピーを提出するので、SNSやメールで予め画像を送付してもらうとよいでしょう。
既に就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」ビザ)を取得している外国人の中途採用の場合でも、それがあなたの会社で働くことができるものとは限りません。必ず専攻した科目と予定される職務の関連性を確認しましょう。
採用した外国人があなたの企業で就労可能かどうか心配な場合は「就労資格証明書交付申請」をして御社で就労可能(または不可能)であることを証明する書類を入管局から発行してもらうことができます。
在留カードの確認
既にメールなどから在留カードのデータを入手されていたとしても、面接時には必ず外国人に在留カード原本の提示を求め、表面で氏名や在留資格、在留期限を確認しましょう。さらに裏面も確認し資格外活動許可取得の有無や最新の住居地を確認しましょう。
表面に住所が記載されていても、転居して転入届をしている場合は最新の住居地が裏面に記載されます。なお、転居後に適切な転入届をしていない場合はビザ申請に悪影響があるので、転入届の有無は確認するようにしてください。
アルバイト事情の確認
留学生の場合、資格外活動許可を取得してアルバイトをしている方が多くいらっしゃいます。
もちろん許可された範囲内でアルバイトをすることは問題ありませんが、風俗営業関連の仕事でアルバイトをしたり、許された時間を超えてアルバイトをしている場合、就労ビザの審査の結果不許可となります。
なかには1つのアルバイト先では1週間に28時間という就労制限を守っていても、アルバイトを掛け持ちしていて合わせると28時間を超えている方もいます。本人に自覚がないことも多いのですが、合計して28時間を超えてアルバイトをしている場合はオーバーワークとなるので面接時に確認しましょう。
実務経験年数の確認
留学生であっても本国で社会人経験のある方もいます。また、中途採用の場合や学歴要件を満たさず職歴で申請をする場合にも必ず実務経験を確認するようにしましょう。
具体的にはどのような業務を何年何ヵ月経験したかを証明書類と共に確認します。証明する資料がない場合、実際に実務経験があったとしても入管局での審査では実務経験年数にはカウントされません。また、アルバイトやパートの実務経験年数もカウントされません。
その他どんなことを面接時に聞けばよいでしょう?
まず日本人の採用と大きく異なる点は、将来外国人が帰国する可能性があることです。そこで、外国人のキャリアプランを聞くとともに、以下のようなことを中心に採用面接を組み立てていくと比較的スムーズとなります。
まずは帰国する予定があるのか、どのように働きたいか、永住まで視野に入れているのかといった、外国人本人が思い描いているキャリアプランを把握することで、採用する側も企業の中でどのように働いてもらうかの青写真を描くことができると思います。 |
はじめての外国人面接のヒントはこちら
STEP5:内定
選考の過程で外国人本人と賃金をはじめとした労働条件を話し合い、双方の合意により内定となります。
その際、採用後のトラブル回避のために、可能な限り日本語の雇用契約書に加え、雇用する外国人の母国語や英語などの言語で翻訳分を作成し、その双方を外国人本人に渡すことを推奨いたします。
なお、就労ビザ取得前に雇用契約を交わすことに抵抗がある方もいらっしゃると思います。その場合は労働条件通知書や内定通知書という形でも構いませんが、記載する項目については雇用契約書に必要な労働法で規定された項目を全て網羅している必要があります。
また、上記資料はビザ申請時の必須書類ですので内定→就労ビザ申請という順番になります。
雇用契約書のサンプルと作成時の注意点はこちら
STEP6:就労ビザ申請
原則として、外国人本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局で外国人本人が申請をします。
1.留学生の外国人を新卒で採用する場合
「留学」から「技術・人文知識・国際業務」ビザへの在留資格変更許可申請を行います。
新卒の外国人の場合、卒業前年の12月から申請受付が開始されます。この時期は申請が重なり入管局が非常に混雑するため、申請してから結果が出るまで1~3カ月程度かかります。
4月1日に入社してもらう場合、1月下旬ごろまでに申請を完了するようなスケジュール感の企業様が多いようです。
2.日本にいる外国人を中途採用する場合(転職前と別職種での採用)
採用予定の外国人に担当してもらう職種・仕事内容に該当する、新しい在留資格へ変更する【在留資格変更許可申請】をするための手続を行います。これは就労ビザの変更を伴う申請ですので、雇用予定の外国人が新しい在留資格に変更することが可能な要件を備えている必要があります。
※出入国在留管理庁は会社の経営規模や外国人の在留状況等様々な角度から審査します。「必要書類を申請すれば必ず在留資格変更が認められる」といった届出制申請でない事を認識しておく必要があります。
3.既に日本にいる外国人を中途採用(転職前と同職種での採用)
転職前に外国人が働いていた職種と転職後の職種が同様な場合、基本的にはビザ申請を行う必要はありませんが、採用する外国人が次回ビザを更新する際には、新たに転職先の企業に関する関係書類を提出し、【在留期間更新許可申請】することになります。
上記の場合、更新時に申請の結果がいきなり不許可になるというリスクもあるので、安心して転職先で働くためにも、「就労資格証明書交付申請」を転職時にすることをおすすめしています。
STEP7:受け入れ準備
就労ビザ取得後は入社日を決定し、勤務するにあたり必要に応じて以下のような受け入れ準備をしていきます。
- 研修・教育カリキュラム作成
- 住居(社宅・借り上げ寮など)の手配
- 日本語スクール
- 配属部署の受け入れ態勢づくり
STEP8:入社後の手続
ハローワークへの届出
外国人を雇用後は雇用会社がハローワークをへ「外国人雇用状況報告」の届出をすることが義務付けられています。これはすべての会社に義務付けられていますので、必ず届出をしてください。届出事項は雇用する外国人の氏名・在留資格・在留期間など基本的なものです。この届出は、雇用の時だけでなく、離職の際にも義務となっています。
所属(契約)機関に関する届出に関する指導
この「所属(契約)機関に関する届出」は、外国人が転職した場合に外国人本人がしなければならない届出です。この届出を怠った場合には20万円以下の罰金に処せられることがあります。
外国人がこの届出のことを知らないことがよくあります。この届出を怠った場合、次回ビザ更新に悪影響があるので、中途採用した場合は雇用会社から外国人に教えてあげてください。
住民登録の指導
外国人従業員の居住地が決まったら、住所を管轄する市区町村役場において、外国人本人が住民登録を行います。
社名変更等届出
雇用会社の社名や住所に変更があった場合、出入国在留管理庁への届出義務がありますので、変更があった場合には忘れずに届け出てください。
この記事を読んだ方は次の記事も読んでます
技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザ必要書類
外国人が転職する場合のビザ申請手続と入管への届出
企業内転勤ビザ
高度専門職ビザ
高度専門職(高度人材)ビザとポイント制
医療ビザ
介護ビザ
教授ビザ
教育ビザ
研究ビザ
外国人の転職と就労資格証明書
外国人雇用と雇用契約書作成時の注意点(サンプル付)
外国人雇用(就労ビザ)でもっとも注意することは?
外国人を採用面接する際の質問事項
外国人雇用状況の届出
外国人と社会保険の適用
外国人と労災保険の適用
外国人のマイナンバーカードについてかんたんに説明
就労ビザと中国の学歴
就労ビザとフランスの学歴
自分でビザ申請する場合との比較
横浜で就労ビザ申請なら
神奈川で就労ビザなら
在留資格一覧
就労ビザの審査期間
ビザ無料相談
自社で働けない外国人に内定を出してしまう雇用主の方も実はたくさんいらっしゃいます。その場合、ビザの申請をしても許可がもらえず、その段階で相談に来る方もいます。
当事務所では採用段階からどのような学生が企業で働くことができるかなど外国人雇用とビザについて総合的にご相談できる「顧問サービス」も行っています。顧問サービス契約中はビザ法務相談を何度でもご利用いただけます。
顧問サービスご相談はこちら
顧問料金表はこちら |
この記事を書いた人
金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
【取材実績】
【講師実績】
|
相談無料です